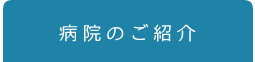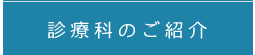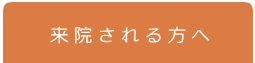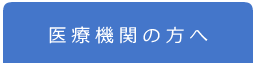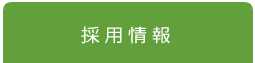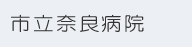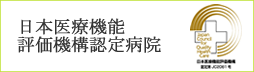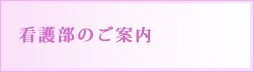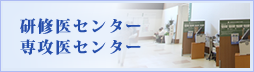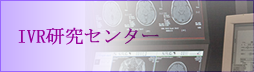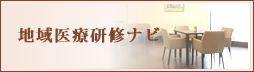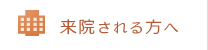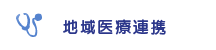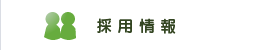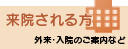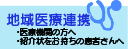臨床検査室
生理検査室 |
心電図 | 心臓の筋肉が発する微弱な信号を波形に置き換え記録する検査です。 形から心臓肥大や心筋梗塞など、リズムから不整脈の種類がわかります。 | |
| 負荷心電図 運動負荷試験  |
階段(2段)を一定のリズムにあわせて数分間昇降します。 運動負荷試験では、ベルトの上を決められた速さと傾斜に合わせ、運動します。 運動の前後や運動中の心電図波形を比較する検査です。 | ||
| ホルター心電図 | 日常生活中の心電図を24時間記録して、解析します。 心電図検査や負荷心電図ではとらえきれない、不整脈や心筋虚血をとらえます。 | ||
| 呼吸機能 精密呼吸機能 |
掛け声に合わせて息を大きく吸ったり吐いたりを繰り返す検査です。
肺活量や一秒量(最大努力で1秒間に吐ける量)がわかります。 |
||
| 脳波 | けいれんを起こした時や、意識障害が見られた時などに行う検査です。 脳から出ている微弱な電波を記録します。 | ||
| 筋電図 (神経伝導速度検査) |
中枢神経や末梢神経の動きを見る検査です。
神経に電気刺激を与えて、伝わる速さや反応の大きさを計測します。 |
||
| 睡眠時無呼吸の検査 |
睡眠時無呼吸症候群の可能性が疑われた場合に行う検査です。 簡易検査では自宅にて、手の指や鼻にセンサーを付けて寝てもらい検査します。 簡易検査よりさらに詳しく調べるには、入院していただき、終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査を行います。PSG検査では、顔や体にセンサーを付けます。 | ||
| 血管の検査 | ABI・CAVI | 両腕・両足首4か所の血圧・脈波を測定します。 動脈硬化や血管のつまりの可能性を調べる検査です。 | |
| 血管拡張反応(FMD) |
心疾患や脳卒中になるリスクである、動脈硬化症に至る前の血管の機能を評価することができます。 動脈硬化は血管内皮機能障害から引き起こされると言われており、その血管内皮機能を調べる検査です。 食事の影響などを除くため、早朝に検査します。 | ||
超音波検査室(エコー) |
頸動脈エコー 上・下肢/動静脈エコー 腎動脈エコー |
皮膚の上にエコーゼリーを塗り超音波を当てて検査対象臓器を画像化する検査です。
臓器の形や性状、動きや血液の流れ等がわかります。
超音波は人体に悪影響は無く、エコーゼリーも無害です
。 |
|
| 心エコー | |||
| 腹部エコー | |||
| 体表エコー | |||
耳鼻科の検査 |
純音検査 | 聞こえの程度を調べる検査です。 低音から高音がどれくらい小さな音から聞こえるかがわかります。 | |
| テインバノメトリー | 耳の中の鼓膜の動きを調べる検査です。 | ||
OAE |
聞こえに関する耳の奥の方にある感覚細胞の反応について調べる検査です。 | ||
| 重心動揺検査 | めまいの検査です。
立った状態で体の揺れの状態を調べます。 |
||
 ☆主な検査項目です☆
☆主な検査項目です☆
この他にも、さまざまな検査をしていますので
詳しくは、各診療科・検査室にお問い合わせください。